【マレーシア子育て奮闘記】子どもの教育を考えたら、自分の価値観も問われた話
こんにちは。オンラインライフコーチングサービス「There Will Be Answers.」代表の常岡です。「ココロとアタマとカラダの声をぜんぶ聴く」をモットーに、あなたが自分らしい人生を歩むためのお手伝いをしています。
実は私、現在マレーシアで10歳になる一人息子を育てています。慣れない海外での子育て、特に教育に関しては、日本にいた頃とは異なる価値観や選択肢に日々向き合い、正直、頭を抱えることも少なくありませんでした。「息子の将来のために何がベストなんだろう…」その問いは、いつしか私自身の生き方や大切にしたいこと、つまり「価値観」を深く見つめ直す大きなきっかけとなりました。
この記事では、マレーシアという多文化社会での子育てを通じて、私が実際に経験した教育方針の迷い、そしてそこから見えてきた「親自身の価値観」との向き合い方について、実体験を交えながらお話しします。一人の父親としての視点に、NLP(神経言語プログラミング)やCBT(認知行動療法)、NVC(非暴力コミュニケーション)といった心理学・コミュニケーション手法をベースにしたライフコーチの視点も加え、皆さんの子育てや人生のヒントになれば幸いです。
1. はじめに:マレーシアの太陽の下、息子の教育と「私」の価値観の狭間で
「インターナショナルスクールがいいのか、それともローカルの学校か…」
「マレーシアの教育システムって、日本の教育とどう違うんだろう?」
「周りのご家庭はどんな教育方針で、うちの子はこれで大丈夫なのかな…」
ここマレーシアで10歳の息子を育てていると、日本にいた頃には想像もしなかった教育の選択肢や課題に直面します。多様な文化が共存するこの国では、教育に対する考え方も本当に様々。子供の教育方針を考えると同時に、親の価値観が、否応なく試される毎日です。日本にいた頃は漠然と「中学、高校、大学を出て、どこかの会社に…」なんて考えていた私も、マレーシアに来てからは「彼の未来は、僕の想像だにしないものになるのではないか?」と、考えるようになりました。
息子の将来を思うあまり、情報を集めれば集めるほど混乱し、焦りを感じる日々。でも、その迷いの先にあったのは、息子の教育問題だけでなく、もっと根深い「私自身の価値観」というテーマだったのです。
この記事では、マレーシアでの子育てという、ある意味特殊な環境だからこそ浮き彫りになった「親の価値観」の問題と、それにどう向き合ってきたのか、そしてライフコーチとして皆さんにどんなヒントをお伝えできるのかを、私のストーリーを通してお話ししたいと思います。

【ライフコーチ的実践ポイント】
子育ての悩みを抱えた時こそ、自分と向き合う絶好の機会です。まず、ノートとペンを用意し、「今、子どもの教育で一番気がかりなことは何か?」「自分が子どもの頃、親にどんな教育をしてもらいたかったか(または、されて嫌だったか)?」という2つの問いに、思いつくまま5分間書き出してみましょう。この作業が、「自分の価値観 見つめ直す きっかけ」となり、漠然とした不安を具体的な言葉にする第一歩です。私自身、マレーシアでの学校選びの際、この書き出し作業で自分の本心に気づかされました。
2. なぜ私たちは子どもの教育方針でこんなに悩むのか? – マレーシアでの経験から見えたこと
子どもの教育方針で悩むのは、日本でもマレーシアでも、きっと多くの親御さんが経験することでしょう。その背景にはいくつかの共通点と、私がマレーシアで特に感じた点があります。
まず、急速な社会の変化と教育選択肢の多様化。これは世界共通の課題かもしれません。グローバル化、非グローバル化、AIの進化…将来何が起こるか分からない時代に、子供の将来を不安に思い、親としてできることを考えれば、親が迷うのは当然です。マレーシアでは、インターナショナルスクール一つとっても、イギリス式、アメリカ式、IB(国際バカロレア)などカリキュラムも様々。選択肢が多い分、何を基準に選べば良いのか、本当に悩みます。
次に、親自身の経験や受けた教育の影響。私自身、昭和の日本の教育システムの中で育ち、子供ながらに「良い成績を取ること」と「協調性を持つこと」を無意識に重視していたように思います。しかし、マレーシアのインターナショナルスクールでは、個々の意見を尊重し、積極的に発言、活動することが求められる文化があります。息子の学校でのグループワーク発表やディスカッションの様子を見て、驚かされるとともに、「日本の教育の良さもあるはずだ」と考えたり。良かれと思って自分の経験を押し付けそうになる危うさを、異文化の中で痛感しました。時代も環境も違う息子の教育は、私にも価値観にも大きな変化をもたらしています。
多くの親は子どもに「目標を持ち、自分で考えて行動できる人」に育ってほしいと願っています。しかし、その「目標」や「行動」の具体的なイメージが、文化や環境によって大きく異なることを、私はマレーシアで学びました。



【ライフコーチ的実践ポイント】
教育情報を集める際は、その情報が「誰によって、どんな目的で発信されているか」を意識的に確認しましょう。情報源の信頼性を吟味する習慣をつけることが大切です。
発信者がどのような時代、どのような環境で育っているかによってその発言の前提が大きく変わります。
また、ご自身の子供時代を振り返り、「親から受けた教育で、今の自分にプラスになっていること」と「逆に、もっとこうしてほしかったこと」をそれぞれ3つずつ書き出してみてください。この作業は、無意識の親の期待がもたらす子供への影響に気づき、客観的に自分を見つめるトレーニングになります。
3. 「自分の価値観」との衝突:マレーシアで息子が教えてくれた大切なこと
息子の教育方針を考えれば考えるほど、私自身の「価値観」と向き合わざるを得ませんでした。
例えば、マレーシアに来た当初、私は息子に「早く英語に慣れて、良い成績を取ってほしい」と強く願っていました。それは、グローバル社会で活躍するためには英語力と学力が不可欠だという、私なりの「価値観」があったからです。息子は日本でインターナショナル保育園に通っていたので、英語については一般的な日本人の子供よりも慣れていたと思います。しかし、息子の最初の担任はインド系の先生。息子は強烈なインドなまりの英語に戸惑い、また、様々な国から来た個性豊かな同級生に翻弄され、なかなか学校に馴染めませんでした。「学校に行きたくない」と言ったことも少なくありません。そんな息子の姿を見て、「私は、息子を追い詰めているだけなのではないか?」と深く悩みました。これは、まさに自分の中での葛藤でした。
ここで言う「価値観」とは、先ほども触れたように、私たちが「何が大切か」「何が正しいか」を判断する基準となる信念です。
価値観の氷山モデルについて
私たちの行動や言葉は、価値観における氷山の一角です。
- 水面上(見える部分): 行動、言葉(例:息子に「もっと勉強しなさい」「ちゃんとしなさい」と言う)
- 水面下(少し見える・感じる部分): 感情(例:息子の現状や将来への不安、焦り)
- さらに水面下(気づきにくい部分): 思考、思い込み(例:「良い成績=幸せな将来」という考え)
- 最も深い層(無意識の奥底): 価値観、信念(例:「安定」「成功」を重視する価値観)
マレーシアでの子育ては、この無意識の価値観を容赦なく刺激し、表面化させました。時にそれは「息子はこうあるべきだ」という「べき思考」や、「この学校に入れないなら意味がない」といった「白黒思考」として現れ、私自身を苦しめました。普段クライアント様に対し「べき思考」や「白黒思考」からの解放をお手伝いしているコーチである私が自らのうちに潜む認知のカタチに直面したのです。
ある日、息子が学校の「インターナショナルデー」というイベントで、ミャンマーの伝統的な踊り(※各学年に様々な国が割り当てられるのです。)を楽しそうに踊っているのを見ました。成績や言葉の壁を気にせず、いろんな国の友達と並んで、ただ純粋に楽しんでいる息子の姿は、私の目を覚まさせるものでした。「この子にとっての幸せは、私の考える幸せとは違う」。よく考えれば当然ともいえるその考えに気づいた瞬間、自分の価値観そのものを見つめ直すきっかけが訪れたのです。



【ライフコーチ的実践ポイント】
日常会話で「~すべき」「~ねばならない」という言葉を使いそうになったら、一度深呼吸をして、その言葉を「~したい」「~だと嬉しい」という表現に置き換えてみましょう。つまり「世間の常識」ではなく「自分の希望」であることに気づくのです。例えば、「あなたはもっと勉強すべきだ」ではなく、「あなたが楽しく学んでいる姿を見られたら、パパは嬉しいな」と。この小さな言い換え練習が、無意識の「べき思考」に気づき、より柔軟な視点を持つ助けになります。
4. 価値観の再発見とアップデート:息子と共にマレーシアで成長する日々
自分の価値観に気づき、それが必ずしも息子にとって最善とは言い切れないと分かった時、次はその価値観を見つめ直し、アップデートしていくプロセスが始まりました。これは、父親として、そして一人の人間として、マレーシアで息子と共に成長していく旅でもありました。
自分自身と向き合う
まず、ノートにちょっとした気づきを書いたり、静かに考える時間を持ったりして、自分の内なる声に耳を傾けました。「私は本当に息子に何を望んでいるのだろう?」「マレーシアで暮らすことの意味は何だろう?」こうした問いに正直に向き合うことで、凝り固まっていた「日本の常識」や「親としてのべき論」が少しずつほぐれていきました。
息子とのコミュニケーションを見直す
息子との関わり方も意識して変えました。ここで役立ったのが、NVC(非暴力コミュニケーション)の考え方です。これは、自分と相手の「感情」と「ニーズ(本当に必要としていること)」に焦点を当てるコミュニケーション。子供の気持ちがわからない時や子供の心に寄り添う方法として、また、マレーシアの多様なバックグラウンドを持つ人々と接する上でも非常に有効だと感じています。
例えば、息子が宿題をやりたがらない時。以前は「なんでちゃんとやらへんの!」と叱っていましたが、NVCを意識してからは、「宿題をしてないのを見て、お父さんはちょっと心配になるねん。学校で怒られて元気のない君を見るのがつらいのよね。早めに宿題やっといてほしいんやけど、なんか手を付けたくない理由とかあるん?」と、私の気持ちと願い(ニーズ)を伝え、息子の気持ちを聞くようにしました。
また、CBT(認知行動療法)の考え方も、私自身の感情コントロールに役立ちました。マレーシアでの生活でバスが大幅に遅れたり、注文したものが何度も間違えられたり、来なかったりという事態に遭遇しイライラした時、「なんでいつもこうなんや!」と考える代わりに、「これは文化の違いだから仕方ない」「この経験から何を学べるだろう」と視点を変えることで、冷静さを保てるようになりました。これは子育てにイライラしないコツとしても応用できると感じています。
こうしたアプローチを通じて、マレーシアで模索する日々です。「正解」を求めるのではなく、目の前の息子をよく観察し、対話し、彼に合った環境を柔軟に創り出す。最近では、息子が興味を持っているyoutube撮影やゲーム実況をサポートし、非認知能力を育む遊びの効果を実感しています。マレーシアでは、学校外の活動も非常に盛んで、様々な選択肢があります。(参考:文部科学省 国立教育政策研究所の報告書などでも非認知能力の重要性が指摘されています。)
共感的なコミュニケーションのためのフレーズ例(我が家の場合)
| 状況 | 以前の私なら… | 今の私が心がけている声かけ |
|---|---|---|
| 息子が学校のことで落ち込んでいる時 | 「ほら、落ち込んでんと元気だして!」「そんなこと気にすんな!」 | 「何かあったんやね。話せる時でいいから、聞かせてくれる?しんどいのね。」 |
| なかなか宿題を始めない時 | 「ちょっといつまで遊んでんの!はよ宿題しなさい!」 | 「宿題の時間だけど、何か他に気になることがあるんか?お父さん宿題しっかりやってほしいんやけど、もし手伝えることがあれば言うてや。」 |
| 新しいことに挑戦するのをためらっている時 | 「何事もやってみんとわからんやろ!頑張って!」 | 「今、不安な気持ちがあるのね。どんなところが心配やとおもう?一緒に考えてみよか。」 |



【ライフコーチ的実践ポイント】
子供の意欲を引き出す言葉かけで悩んだら、まず1日5分、「評価しない聴き役」に徹する時間を作りましょう。子どもの話に「それは良いね」「それはダメだね」といったジャッジを挟まず、「うんうん」「そうなんだね」と相槌を打ちながら、ただ耳を傾けます。これが信頼関係を深め、子どもが本音を話しやすくなる土壌を作ります。
5. これからの子育てと「私らしい生き方」の調和 – マレーシアで見つけた光
マレーシアでの子育てを通じて自分の価値観と向き合う経験は、私自身の生き方を見つめ直す大きな転機となっています。
息子に「自分らしく生きてほしい」と願うなら、まず私自身が「自分らしく生きる」姿を見せることが何より大切だと気づきました。親が自分を認め、人生を楽しんでいれば、子どもも安心して「自分らしさを追求していいんだ」と思えます。マレーシアに来て、様々な生き方をしている人々と出会い、「こうでなければならない」という枠が外れたように感じます。これが子供の自己肯定感を高める関わり方の原点なのかもしれません。
以前は「息子のために」と自分のキャリアや趣味を後回しにすることも厭わないと考えていましたが、今は自分の時間も大切にし、ライフコーチとしての活動や、マレーシアでの新しい挑戦を楽しんでいます。その方が結果的に、息子にも穏やかに、そして前向きに関われるようになりました。
子育ては、日本でもマレーシアでも、時に大変で悩むことも多い道のりです。でもそれは、親も子も共に成長し、人生をより豊かにしていく素晴らしい旅。息子の教育というテーマは、最終的に「自分はどう生きたいのか」という問いに繋がり、マレーシアという地で、私らしい人生の舵を握る感覚を取り戻させてくれました。「この子にどんな世界を見せてあげたいか」という、私自身の価値観に繋がっているのです。



【ライフコーチ的実践ポイント】
反抗期にどう対応すればいいんだろう、といった将来の不安や、子供の声掛けの適切な方法がわからないという悩みに直面した時こそ、自分自身の「幸せの定義」を明確にするチャンスです。ノートに「私が心から幸せを感じる瞬間トップ3」を書き出してみましょう。そして、その幸せを実現するために、今日からできる小さな行動を1つだけ決めて実行します。例えば、「好きな音楽を聴く時間を15分作る」「自然の中を散歩する」など。自分自身が満たされることが、結果として子どもへのより良い関わり方に繋がります。
6. まとめ:迷いは成長のチャンス。あなたらしい答えを、マレーシアの空の下で見つけよう
マレーシアでの子育ては、私の価値観を根底から揺るがしました。しかし、その迷いや葛藤こそが、自分自身を見つめ直し、息子と共に成長するための貴重な機会となったのです。
完璧な教育も、誰にでも当てはまる唯一の正解もありません。特にマレーシアのような多様な環境ではなおさらです。大切なのは、情報を集めつつもそれに振り回されず、目の前の息子をよく見て、そして何よりも自分自身の心の声に耳を傾け、私たち家族にとっての「最善」を見つけていくプロセスです。
この記事でお伝えした、マレーシアでの私の個人的な経験と気づきが、少しでもあなたの肩の荷を下ろし、前向きな一歩を踏み出すためのお役に立てれば幸いです。



【ライフコーチ的実践ポイント】
今日この記事を読んで、心に響いたことや「試してみよう」と思ったことを、スマートフォンや手帳にメモしてみましょう。そして、その中から最も簡単に取り組めそうなことを1つ選び、「いつ」「どこで」「どのように」実践するかを具体的に計画します。例えば、「今夜、夕食の時に子どもの話を笑顔で聞く」「週末に、パートナーと教育について話す時間を15分確保する」など。小さな行動の積み重ねが、やがて大きな変化を生み出します。
7. あなたの「ココロとアタマとカラダの声」を聴かせてください。 – マレーシアからサポートします
ここまで私のマレーシアでの子育てストーリーを読んでくださり、ありがとうございました。
子どもの教育、そしてご自身の価値観について、様々な想いが巡ったかもしれませんね。特に海外での子育ては、日本とは違う悩みや孤独を感じることもあるかと思います。
「頭では分かっているけど、なかなか行動に移せない」
「誰かに話を聞いてほしいけど、海外だとなかなか相談相手が見つからない」
「もっと自分らしい子育てや生き方を、異文化の中で見つけたい」
もしあなたが今、そんな風に感じているなら、一度、私、常岡とお話ししてみませんか?
私はマレーシアにいますが、オンラインで、世界中どこからでもセッションが可能です。
オンラインライフコーチングサービス「There Will Be Answers.」では、「ココロとアタマとカラダの声をぜんぶ聴く」ことを大切にしながら、あなたが本当に望む未来へ進むためのお手伝いをしています。
コーチングは、ティーチング(教える)やカウンセリング(癒す)とは異なり、あなたの中にある「答え」を引き出すプロセスです。対話を通じて、あなたの思考を整理し、隠れた強みや可能性に光を当て、具体的な行動計画を一緒に立てていきます。特に海外での生活や子育てにおける特有の悩みにも、私自身の経験を踏まえて寄り添うことができます。
特に、
- 海外(もちろん日本国内も)での子育ての方針に迷い、自分の軸を見つけたい方
- 自分の価値観と向き合い、より自分らしい生き方を実現したい方
- 異文化の中での夫婦間や親子間のコミュニケーションを改善したい方
- 漠然とした不安やストレスを解消し、前向きな毎日を送りたい方
このような方々から、ご好評をいただいています。
初回は、あなたの現状やお悩みをじっくりお聴きする体験セッションをご用意しています(詳細はホームページをご確認ください)。無理な勧誘は一切ありませんので、安心してお気軽にお問い合わせください。
あなたのココロとアタマとカラダの声に、じっくりと耳を傾ける時間。
それが、新しいあなたに出会うための一歩になるかもしれません。
詳細は、ぜひ当サービスのホームページをご覧ください。
https://terewillbeanswersx.com
あなたからのご連絡を、マレーシアの地より心からお待ちしています。
オンラインライフコーチングサービス There Will Be Answers.
代表ライフコーチ 常岡
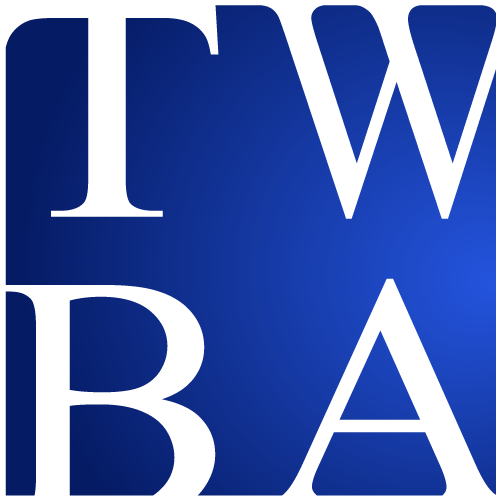


コメント