【実体験】マレーシア移住のカルチャーショック19選!「驚き」を「成長」に変える適応術
「マレーシアといっても、クアラルンプールは都会だから東京や大阪とあんまり変わりないはず」…のはずが、日常のあちこちで「アレ?なんだコレ!?」の連続。
日本では考えられないような出来事に遭遇し、「えっ!?」と驚いたり、「なんやねん!」とモヤモヤすることも。
- 公衆トイレに紙がない!どうするの?
- 頼んだコーヒーと違うのが来た…しかも売り切れって今言う!?
- 夜中に突然、窓の外で巨大な花火が…!?
- え、G(あの黒い虫)多くない!?
そう、それこそが多くの移住者が体験する「カルチャーショック」。大阪から、クアラルンプールに家族で移住してきた、私自身も日々体験していますし、海外移住ライフコーチとしてたくさんの移住者の方々のお話を聞く中で、「あるある!」「わかるわかる!」と頷くことばかりです。
こんにちは!「ココロとアタマとカラダの声をぜんぶ聴く」オンラインライフコーチングサービス There Will Be Answers. 代表の常岡です。(https://terewillbeanswersx.com)
この記事では、私や家族のリアルな体験談をもとに、マレーシア移住者が直面しがちなカルチャーギャップ19選を厳選してご紹介します。良い面も、ちょっと困った面も含めて、リアルな生の声をお届けします!
でも、ただ「驚いたこと」を並べるだけではありません。せっかくなのでライフコーチ視点でお届けしたいと思います。この記事を読めば、
- なぜ「?」と感じるのか、その背景にある文化や理由がわかる
- 移住者がどうやって乗り越えているのか、具体的な工夫がわかる
- ライフコーチ視点の「適応術」で、ストレスを減らし、成長の種にする方法がわかる
ようになります。
この「驚き」や「戸惑い」、そして「感動」は、自分自身を見つめ直し、新しい価値観に触れ、人として大きく成長するための「ギフト」 なんです。
さあ、私と一緒に、泣き笑いのマレーシアでのカルチャーショックを見ていきましょう!あなたのマレーシア生活が、もっと豊かで、もっと自分らしく輝くためのヒントが、きっと見つかるはずです。
第一章:日常に潜む「あれ?」の正体 – マレーシア暮らしのリアル
まずは、日々の暮らしの中で「えっ?」となる習慣やインフラの違いから。日本の常識が通用しない場面に、どう向き合えばいいのでしょう?
1. 左手は不浄?トイレと食事のマナー
ショッピングモールやレストランのトイレに入って、まず探すのがトイレットペーパー。でも、個室に備え付けられていないことが多く、代わりに壁にハンドシャワー(通称:お尻シャワー)が付いています。手持ちのウォシュレットと言えばいいのでしょうか。これはイスラム教の「水で洗い清める」という教えに基づく習慣。紙で拭くより水で洗った方が清潔という発想(まあ、確かに)。最初は、床が水浸しになっていることもあって「びしゃびしゃやんか!」と抵抗を感じました。僕のお出かけリュックの中には大きめのポケットティッシュが標準装備してあります。
また、食事の場面では右手を使うのが基本。特にマレー系の友人との食事や、手で食べる文化(手食)に触れる際は、左手で食べ物を触らないように意識します。僕は左利きなので、ちょっと大変なんですが。握手や物の受け渡しも右手で行うのが礼儀。郷に入っては…と頭では理解しつつも、慣れるまでは意識が必要です。屋台や露店では、手洗い場が無いことも多く、アルコールティッシュも必需品です。お酒を飲むことが禁じられているムスリム(イスラム教徒)の方でも、手指を清める目的での使用はOKだそうです。
2. 「土間」がない玄関?靴を脱ぐ場所と習慣のギャップ
日本の家には、洋風建築でも、マンションでも当たり前にある玄関の「土間」。靴を脱いで家に上がる、という点ではマレーシアも同じですが、多くのコンドミニアムではドアを開けるとすぐにリビングや廊下が広がっています。じゃあ靴はどこで?答えは「ドアの外」。共用廊下に靴箱を置いたり、そのまま脱いだりするのが一般的です。雨の日に濡れた靴を外に置くのは合理的かもしれませんが、衛生観念の違いから、日本人としては少し抵抗を感じるポイント。
ウチはドアの内側に大きな玄関マットを敷いて「擬似土間」を作り、そこで脱ぎ履きするようにしています。それでも、宅配や修理の人が習慣で外で脱ぎ、裸足でマットを通過していくことも…。その度に「あー!」と思いますが、これも文化の違い、と割り切る心の修行中です(笑)。
3. 時刻表はナシ?電光掲示板の「あと3分」は「あと40分」?
クアラルンプール市内を走る路線バス「Rapid KL」。市民の重要な移動手段ですが、バス停での待ち時間は予測不能なことが多いです。バス停にある電光掲示板の到着予定時刻、「あと3分」と表示されていたのに、一向に来る気配がなく、掲示板の数字はそのまま。最終的に40分待った…なんて経験も一度や二度ではありません。
バスの位置情報をリアルタイムで追跡できるはずのアプリ「Moovit」や「PULSE」も、残念ながら表示が実際のバスの位置と大きくズレていることがしばしば。「来る」と信じて待つしかない、そんな状況もしばしばです。時間に正確な日本の交通機関に慣れていると、この読めなさは大きなストレス。バスを利用する際は、時間に十分すぎるほどの余裕を持つか、他の交通手段(Grabなど)を検討するのが吉です。
4. ぼんやり待つと素通り?バス乗車の流儀
長い時間待って、ようやくお目当てのバスが見えた!これで一安心…と思ったら大間違い。マレーシアのバスは、バス停でただ立って待っているだけだと、乗る意思がないと思われて素通りされてしまうことがあるんです!私も最初は呆然と見送ってしまいました。乗りたいバスが近づいてきたら、タクシーを止める時のように、はっきりと手を挙げて「乗ります!」と運転手さんにアピールすることが必須です。
これをしないと、目の前を無情にも通過していくバスを眺める羽目に…。また、車両によってはかなり年季が入っており、日本では考えられませんが、乗降ドアが半開き、あるいは全開のまま走り出すなんていうワイルドな光景に遭遇することも。スリル満点ですが、安全面ではちょっと心配になりますね。
5. ゴミの分別があまりない
燃えるゴミ、燃えないゴミ、ビン、カン、ペットボトル…日本では当たり前の細かいゴミ分別。マレーシアに来て驚いたのは、多くの地域やコンドミニアムでは、基本的にすべてのゴミを一つの大きなゴミ箱やダストシュートにまとめて捨てるというルールです。リサイクルに対する意識やインフラ整備も、日本とは大きく違う、という印象。環境問題に関心があると、この「まとめてポイ」には正直、罪悪感が湧いてきます。コンドミニアムによってはリサイクルボックスが設置されている場合もあるので、私は可能な範囲で分別するようにしていますが、これも郷に入っては郷に従えですね。
6. 虫が多い!宿敵「G」との遭遇と共存?
これは多くの移住者が「洗礼」として経験することかもしれません。そう、G(あの黒くて素早い虫…!)との遭遇率が、日本とは比較にならないほど高いのです。私もマレーシアに来てから、日本での生涯遭遇数を最初の数ヶ月で更新しました(笑)。Gだけでなく、行列を作るアリ(しかも種類が多い!)や、名前もわからないような小さな虫たちと、家の中で出くわすこともしばしば。
虫よけスプレーはもちろん、壁や床に塗るタイプの虫よけチョークや、アリの通り道に置く甘いシロップ状の駆除剤(アリメツ)などを駆使して対策した結果、かなり出現頻度は減りました。それでも油断するとすぐ現れる彼ら…。今ではすっかり見慣れてしまい、悲鳴を上げることもなくなりましたが(笑)、快適に暮らすためには継続的な対策が欠かせません。
ライフコーチング的カルチャーギャップ適応術①:『期待』を手放し、現実と向き合う

完璧なインフラを期待しない: 日本の便利さや清潔さを基準にすると、ストレスが溜まるだけ。「ここは異国」と割り切り、ある程度の不便さや違いはデフォルトと考えましょう。理想と現実のギャップを受け入れることから始まります。
情報収集と対策を: バスのアプリ情報が不正確なら、時間に余裕を持つ。虫が多いなら、効果的な対策グッズを探し、試してみる。現実を受け入れた上で、自分にできる対策を考え、主体的に行動することが大切です。文句を言ったところで状況は変わりませんね。(さんざん言いましたが)
ユーモアを忘れずに: ドアが開いたまま走るバス、突然現れるG…日本ではありえないような出来事も、笑い飛ばせるくらいのユーモアがあれば、ストレスも軽減されます。「ブログのネタができた!」「友人との笑い話にしよう」くらいに思えると、メンタル的にかなり楽になります。
「まあ、いっか」の精神: どうにもならないこと、自分の力ではコントロールできないこと(時刻通りに来ないバス、他人のゴミ出しルールなど)に対して、いつまでもイライラせず「まあ、いっか」「仕方ないな」と受け流す。心の平穏を保つための重要なスキルです。
小さな工夫を楽しむ: 「擬似土間」を作る、効果的な虫対策グッズを見つける、バス待ち時間を有効活用する方法を考える…不便な状況の中で、自分なりの工夫や改善策を見つけて、それをゲームのように楽しむ視点を持つと、適応プロセス自体が面白くなります。
第二章:食卓は驚きの連続!味覚と注文のギャップ
食べることは毎日の楽しみ!でも、マレーシアの食卓では、味覚の違いだけでなく、注文システムにも驚きが潜んでいます。
7. 驚くほど甘い飲み物
マレーシアのローカルカフェ「コピティアム」で、何も考えずに「テー(Teh=紅茶)」や「コピ(Kopi=コーヒー)」を頼むと、その強烈な甘さに驚くこと間違いなし!デフォルトで加糖練乳(コンデンスミルク)と砂糖がたっぷり入っているのが標準なんです。日本の感覚でいると「え、これデザート?」と思うほどの甘さ。無糖が飲みたい場合は「コソン(Kosong=ゼロ、空っぽ)」、甘さ控えめが良い場合は「クランマニス(Kurang Manis)」と、注文時にしっかり伝える必要があります。「less sugar」は日本の「甘口」と心得ましょう。
この「甘さ指定」は、マレーシア生活の必須スキル。最初は面倒に感じるかもしれませんが、自分の好みを明確に伝える良い練習になります。ペットボトルの緑茶も加糖が基本。「sugarless」表記を目印に買いましょう。ちなみに、泡立てたミルクティー「テー・タレッ(Teh Tarik)」は、高いところから注ぐパフォーマンスも楽しく、甘いけど美味しいですよ!
8. ハラル(Halal)への配慮
レストランの入り口やスーパーの食品パッケージで、アラビア文字のようなマークを見たことはありませんか?それが「ハラル(Halal)」認証マーク。マレーシアはもちろんインドネシアやサウジアラビア、ベトナムなどそれぞれの国のハラル認証マークがあります。このマークがついていれば、イスラム教徒が口にすることが「許された」食品であることを示しています。
マレーシアは国教がイスラム教なので、ハラル対応のお店や食品が非常に多いのが特徴。ムスリムは豚肉やアルコールを口にしないため、ハラルのお店ではそれらは提供されません。スーパーでも、お酒や豚肉、豚エキスが含まれる商品(ゼラチンなど)の売り場は「ノンハラル(Non-Halal)」セクションとして明確に区別されています。レジも別で、ムスリムでない方が担当されています。ムスリムの友人を食事に誘う際は、ハラルのお店を選ぶのが基本的なマナー。ハラルの概念を理解し、配慮することは、マレーシアの文化を理解し、多様な人々と良好な関係を築く上でとても大切です。
9. 屋台文化(ホーカーセンター)の活気と衛生観念
マレーシアの食文化を語る上で欠かせないのが「ホーカーセンター」や「パサールマラム(夜市)」と呼ばれる屋台街。マレー料理、中華料理、インド料理など、様々なジャンルのローカルフードが、驚くほど安い値段で楽しめます。その活気ある雰囲気、漂ってくる美味しそうな匂いは、まさに食のワンダーランド!私も大好きでよく利用します。
私が初めてホーカーに行ったとき、注文方法がわからずまごまごしていたら、親切なおじさんが代わりに注文してくれて、飲み物はごちそうしてくれました!マレーシアに来て間もない頃だったので、なんだか泣けるほどうれしかったです。
ただ、日本の衛生基準に慣れていると、テーブルの汚れ具合や、共用の食器の扱いなどが気になる場面も正直あります。厨房は見ないようにしましょう。そんな時は、アルコールティッシュでテーブルやカトラリーを拭いたり、手指消毒をしたり、いつも地元の人で賑わっている人気店(=食材の回転が速く、鮮度と味が良い可能性が高い)を選ぶようにしています。多少のワイルドさも含めて、ホーカー体験を楽しんでいます。
10. 頼んだものが出てこない?レストランでは一期一会
これはマレーシアで外食をしていると、かなりの確率で遭遇する「あるある」かもしれません。レストランで注文したのに、なかなか料理が出てこない。心配になって店員さんに確認すると、「今から作るところだよ」とか、しばらく厨房で確認した後「すみません、それ、もう売り切れました(Sorry, finished already)」と、注文してからかなり時間が経った後に言われることも…。アイスコーヒーを頼んだのにホットコーヒーが出てきたり、頼んでいない料理が運ばれてきたりするのも日常茶飯事。悪気はない(ことが多い)のですが、日本のような正確なサービスを期待すると疲れてしまいます。「まあ、そんなこともあるか」「これもマレーシアだ」と、ある種の「一期一会」を楽しむくらいの、おおらかな心構えが必要かもしれませんね(笑)。
といいつつ、最近はテーブルのQRコードで注文できる店舗がほとんどなので、そっちを使うようになりました。(それはそれで、使い方がややこしいのですが)
ライフコーチング的カルチャーギャップ適応術②:プロセスを楽しみ、結果にこだわりすぎない



期待値を調整する: 注文が100%正確に出てくる、ドリンクがすぐに来る、とは限りません。最初から「間違ってても、まあ仕方ないか」「時間がかかるかも」くらいの心構えでいると、イライラが格段に減ります。「ちゃんと」を求めても疲れるだけです。
確認とリマインドは穏やかに: 注文がなかなか来ない時や、違うものが来た時は、感情的にならずに、「Excuse me, I ordered 〇〇. Could you check?」のように、店員さんに穏やかに確認しましょう。日本のように「すみませーん!」と大きな声で店員さんを呼ぶことはマナーとして失礼に当たるので控えましょう。
「一期一会」の精神で味わう: たとえ注文と違う料理が出てきても、もしそれが食べられそうなものなら、新しい味との出会いを楽しむチャンスと捉えてみるのはどうでしょう?その場の状況を楽しむ柔軟性を持つ。私はこれでたくさんの新しい食べ物と出会いました!
「No problem」は魔法の言葉?: 明らかな間違いでも、もし自分自身が「まあ、これでもいいか」と思える範囲なら、「No problem」と言って受け入れる寛容さも時には有効。こだわりすぎないことが、自分自身の心の平穏に繋がります。
情報共有で賢く選択: 移住者のコミュニティ(オンライン・オフライン)で、「このお店はサービスが良いよ」「ここはよく間違えるから注意」といったリアルな情報を交換するのも、ストレスを避けるための賢い方法です。
第三章:心温まる交流と戸惑い – マレーシアの人々との関わり
マレーシア生活の魅力は、なんといっても「人」。温かい人々との交流に心癒される一方、コミュニケーションスタイルや習慣の違いに戸惑うことも。
11. 多言語・多国籍が飛び交う環境
オフィスで、カフェで、学校で、街中で…マレー語、英語、中国語(北京語、広東語、福建語など)、タミル語といった言語が日常的に飛び交っています。まさにマルチリンガル国家!さらに、特にクアラルンプールのような都市部では、マレーシア人だけでなく、世界中からの駐在員、留学生、長期滞在ビザ保有者など、様々な国籍の人々が暮らしています。そのため、見た目や肌の色、話す言葉の訛りだけでは、相手のバックグラウンドを判断することはほぼ不可能です。「この人は〇〇人に違いない」という先入観は捨て、目の前の相手を「一人のユニークな個人」として捉え、オープンな心で接することが大切。この多様性こそが、マレーシアの面白さであり、自分の視野を広げる絶好の機会です。
12. 相づちや返事が曖昧?「Can Lah!」のニュアンス
誰かに何かをお願いした時、「Can Can!」「Can Lah!(キャン・ラー!=できるよ!)」と明るく返事が返ってくることがあります。でも、この「Can Lah!」、必ずしも「100%確実、絶対にやります!」という意味ではない場合があるので注意が必要。「たぶんできると思うよ」「やってみるよ」くらいの軽いニュアンスのことも。
また、日本人のように頻繁に相づちを打つ習慣がない人も多く、話を聞いてくれているのか不安になることも。直接的な「No」を避けることで相手の面子を保ったり、対立を避けたりする文化的な背景もあります。重要な依頼や確認事項は、後で「〇〇の件、どうなっていますか?」とフォローアップしたり、具体的な期限や内容を明確にして再度確認したりする工夫が必要です。
同様に店員さんに商品の場所を訪ねた時「Nothing(ないよ)」と言われても、その店員さんが知らないだけのこともあるので、もう一度よく探してみましょう。
13. フレンドリーだけど、距離感が近い?
マレーシアの人々は、初対面でもとてもフレンドリーで気さくに話しかけてくれることが多いです。これは本当に嬉しいこと!ただ、時にその距離感の近さに驚くことも。例えば、年齢や結婚の有無、子供の数、時には給料のことまで、日本ではかなりプライベートとされるような質問を悪気なく聞いてくることがあります。
また、私が出会った年配の方は「Hi, Boss!」と肩や腕をがっちり組んできたり、物理的なパーソナルスペースが日本人の感覚より近かったりすることも。
これらは親しみを込めたコミュニケーションの一環であることが多いのですが、もし不快に感じたり、答えたくない質問だったりした場合は、笑顔で「それは秘密です!」と冗談ぽくかわしたり、うまく話題を変えたりするスキルも必要。自分の心地よい境界線を守ることも大切です。
14. 「ボス」や「アンコー/アンティ」と呼ぶ文化
ローカルな食堂やお店で、店員さんや店主のことを「ボス!(Boss!)」と呼んでいるのを聞いたことはありませんか?これは、相手への軽い敬意や親しみを込めた呼びかけとして、日常的によく使われています。また、血縁関係がなくても、年配の男性を「アンコー(Uncle)」、年配の女性を「アンティ(Auntie)」と呼ぶのも一般的。これも年長者への敬意と、コミュニティ内での親密さを示す、アジアの多くの文化に共通する温かい習慣です。
自分が「ボス」と呼ばれたり、いずれ「アンコー」と呼ばれるようになったりするのも、マレーシアに溶け込んでいる証拠かもしれませんね。私はタクシーのドライバーさんや、修理業者の方に「Hi, Boss!」と呼ばれびっくりしました。最初は少し驚くかもしれませんが、こうした呼び方に慣れると、ローカルの人々とのコミュニケーションがよりスムーズで楽しくなります。
15. 多民族ならではの配慮(センシティブな話題)
マレーシアで生活する上で、最も注意が必要なことの一つが、宗教や民族に関する話題です。マレー系(主にイスラム教)、中華系(主に仏教・道教)、インド系(主にヒンドゥー教)など。もちろんキリスト教などそれ以外の信仰の方もおられます。など、多様な民族と宗教が共存しているこの国では、公の場で特定の民族や宗教を比較したり、批判したり、冗談のネタにしたりすることは非常にタブー視されています。(プライベートな場では結構聞きますが、私からは何も言いません。)
これは、過去の民族間対立の歴史も踏まえ、社会の調和と安定を維持するために不可欠な配慮とされています。政治に関する話題も、民族や宗教と絡み合っていることが多いため、公の場では慎重になるべきでしょう。移住者としては、常に敬意と謙虚さを持ち、分からないことは信頼できる人に尋ねるなど、学び続ける姿勢が大切です。
16. とっても親切!人の温かさに触れる日々
戸惑うギャップも多いマレーシアですが、それ以上に日々感じるのが人々の温かさと親切さです。電車に乗れば、子供連れの私達にすぐに、しかも親子3人分席を譲ってくれる人がいたり、降りる駅を教えてくれたり。コーヒースタンドで小銭が足りなかった時、店員さんが「いいよ、私が出しとくから」と言ってくれたこともありました。道で困っていると、私のつたない英語が通じなくても身振り手振りで一生懸命助けようとしてくれる人もたくさんいます。特に子供に対しては、本当にみんな優しくて、気軽に声をかけたり、笑顔を向けてくれたり。日本ではなかなか経験できないような、ストレートで温かい人の繋がりを感じられる瞬間が多く、心がじんわりと温かくなります。これはマレーシアの大きな魅力の一つですね。
17. 日本語しゃべる人いっぱいいる!嬉しい驚き
「海外に出たら、日本語は通じない」…そう思っていましたが、マレーシア、特にクアラルンプールでは、意外なほど日本語を話せる人に出会う機会が多いことに驚きました。日系企業が多く進出しているため、駐在員や現地採用の日本人だけでなく、そうした企業で働くマレーシア人の方々も日本語が堪能だったりします。息子のインターナショナルスクールで、他の保護者の方(マレーシア人)から流暢な日本語で話しかけられてビックリしたことも。また、大学で日本語を学んでいる学生さんや、アニメやJ-POPが好きで独学で日本語を覚えたという若者、日本への留学や就職を目指している方々も少なくありません。異国の地で日本語でのコミュニケーションが取れると、やはり安心しますし、嬉しい驚きです。
ライフコーチング的カルチャーギャップ適応術③:「違い」も「温かさ」も、まるごと味わう



感謝の気持ちを言葉と態度で: 親切にしてもらったら、「Terima kasih(ありがとう)」と最高の笑顔で伝えましょう。目を見て感謝を伝えることで、ポジティブなエネルギーが循環します。その温かい経験を心に刻みましょう。
決めつけず、背景を想像する: 曖昧な返事や距離感の違いも、「なぜだろう?」と一歩引いて考えてみる。文化的な背景や、相手なりの配慮があるのかもしれない、と想像力を働かせることで、無用な誤解やストレスを防げます。
オープンハートで一歩前へ: 様々な背景を持つ人々との出会いは、自分の世界を豊かにするチャンス。少しだけ勇気を出して、自分から挨拶したり、簡単な質問をしたりしてみましょう。笑顔は世界共通の言語です。
自分の「心地よさ」も尊重する: フレンドリーさは嬉しいけれど、いつも合わせていると疲れてしまうことも。自分のエネルギーレベルや気分に合わせて、交流の度合いを調整することも大切。時には一人になる時間も必要です。
ポジティブな経験を数える: 戸惑うことやネガティブな経験に意識が向きがちですが、意識的に「嬉しかったこと」「感動したこと」「親切にされたこと」を数え、記録してみましょう。心のバランスシートがプラスになり、マレーシア生活への肯定感が高まります。
第四章:まさかの光景!?驚きの習慣とインフラ
「え、こんなことある!?」と思わず二度見、いや三度見してしまうような、マレーシアならではの驚きの光景や習慣をご紹介。
18. 一年中お祭り気分?多様すぎる祝日
マレーシアのカレンダーを見ると、本当に祝日が多いことに驚きます。イスラム教のハリラヤ・プアサ(断食明け大祭)やハリラヤ・ハジ(犠牲祭)、中華系の旧正月、インド系のディーパバリ、キリスト教のクリスマス、仏教のウェサックデーなど、主要な民族・宗教の大きなお祭りが国の祝日として定められています。
これに加えて、国王誕生日や各州のスルタン(王様)の誕生日、労働者の日(メーデー)などもあり、年間を通して「お休みモード」の時期が多い印象。時には政府が突然「明日休み!」と宣言することも。お店や役所が閉まって不便な時もありますが、この祝日の多さは、マレーシアの多文化共生を象徴しているようで、なんだか誇らしい気持ちにもなります。
息子は1年の半分がお休みで、大変喜んでおります。
19. 花火がヤバイ!日常に響く爆音
これは、私がマレーシアに来て最も衝撃を受けたことの一つです。お祭りや祝日はもちろん、時には何でもない普通の夜にも、突然、近所で花火が打ち上がるんです。しかも、日本の花火大会のような規模ではなく、個人が自宅の前や空き地で、かなり本格的な打ち上げ花火をボンボン上げていることが多い!コンドミニアムのすぐ前の道から打ち上げられることもあり、窓の外でドーン!と花火が炸裂し、「干してる洗濯もん、焦げるんとちゃうか!?」と肝を冷やすこともしばしば。
さらに驚いたのは、コンドミニアムの高層階の窓から直接、虚空へ花火を打ち上げているのを目撃したことも…。夜遅くまで続く爆音で眠れないこともあり、正直、「うるさいわぁ…」と感じることも。日本では考えられないこの自由すぎる(?)花火文化には、未だに慣れません…。
ライフコーチング的カルチャーギャップ適応術④:驚きをエンタメに変える!



ネタ帳は心の安定剤: 「こんなことがあった!」という驚きの体験、特に理解不能な出来事は、ブログやSNSのネタ、友人との笑い話の「鉄板ネタ」としてストックしましょう。人に話したり書いたりすることで、客観視でき、感情が整理されます。私はポッドキャストのネタが切れなくて助かっています。
「これもマレーシア」の魔法: 理不尽に感じること、日本ではありえないことも、「まあ、これがマレーシアだからな!」と、ある種のエンターテイメントとして捉える。深刻になりすぎず、面白がる視点を持つことで、ストレス耐性が上がります。
安全第一は絶対: 花火が近すぎる、運転が荒いなど、身の危険を感じる場合は、面白がる前にまず安全確保を最優先!洗濯物を屋内にしまう。危険な場所からは離れる、安全な手段を選ぶなど、冷静な判断が必要です。
ポジティブな驚きも記録する: 祝日の多さ、予期せぬ親切、美味しい発見など、ポジティブな「驚き」や「感動」も、意識的に心に留め、できれば記録しておきましょう。ネガティブな出来事とのバランスを取る上で非常に有効です。
ユーモアは最強の武器: 理解できない文化や習慣に対して、真面目に悩みすぎるのではなく、「プッ」と笑えるようなユーモアのセンスを磨く。笑いはストレスを吹き飛ばし、状況を乗り越える力をくれます。
まとめ:カルチャーショックは、あなたを成長させる「宝の地図」
さて、マレーシアでのカルチャーショック19景、いかがでしたか?
「わかる!」「私も経験した!」と頷きながら、時には笑い、時には「うーん…」と考え込んでいただけたでしょうか?これからマレーシア移住を考えておられる方には、参考になれば幸いです。
異文化の中で「当たり前」が揺さぶられる体験は、時に私たちを不安にさせ、疲れさせるかもしれません。でも、私がライフコーチとして確信しているのは、その「ギャップ」こそが、私たちに新しい視点を与え、内なる強さを引き出し、人間的な深みを与えてくれる「宝の地図」のようなものだということです。
- 「違い」を知ることで、自分自身の輪郭がはっきりする。
- 「戸惑い」を通して、多様性を受け入れる心が育まれる。
- 「思い通りにいかない」経験が、しなやかな適応力を鍛えてくれる。
- 「温かさ」に触れることで、感謝と喜びの感度が上がる。
マレーシアでの毎日は、まさに「ココロとアタマとカラダの声ぜんぶ」で、異文化と、そして自分自身と対話する、かけがえのない学びの連続です。
もしあなたが今、カルチャーショックの真っ只中で、「しんどいな…」と感じているなら、それはあなたがまさに成長しようとしているサインなのかもしれません。
そのプロセスを、もっとスムーズに、もっと楽しく、もっと自分らしく進むために、専門家のサポートを活用することも考えてみませんか?
PR:あなたのマレーシア生活、もっと輝かせるお手伝いをさせてください
マレーシアでの新生活、異文化の中での挑戦、キャリア、人間関係…もしあなたが今、何かに悩み、立ち止まっているなら、一人で抱え込まないでください。
オンラインライフコーチング There Will Be Answers.では、オンラインの安心空間であなたの気持ちや考えをじっくりお聴きし、あなたが本当に望む未来へ向かうための具体的な一歩を見つけるお手伝いをします。NLP、CBT、NVCといった心理学の知恵を背景に持ちながらも、難しい言葉は使わず、あなたの心に寄り添う対話を大切にしています。
私のコーチングで、あなたはこんな変化を期待できます:
- カルチャーショックを乗り越え、異文化適応を「楽しむ」ことができるように。
- ストレスや不安と上手に付き合い、心の平穏を取り戻せるように。
- 多様な人々の中で自分らしく輝き、円滑なコミュニケーションが取れるように。
- 海外生活でのキャリアや人生の目標が明確になり、実現に向けて動き出せるように。
- 自己肯定感が高まり、自信を持って毎日を送れるように。
「コーチングって初めてだけど…」「常岡さんってどんな人?」
少しでも興味を持っていただけたら、ぜひ初回体験セッションにお越しください。オンラインなので、どこからでも繋がれます。まずは、あなたの声を聞かせてください。
YouTubeもやってますので、よかったらのぞいて見てください。私の人となりを知っていただけると思います。
あなたがマレーシアという素晴らしい舞台で、自分らしい最高の物語を紡いでいくことを、心から応援しています!
詳細・お問い合わせ・お申し込みはこちらから↓
https://terewillbeanswersx.com
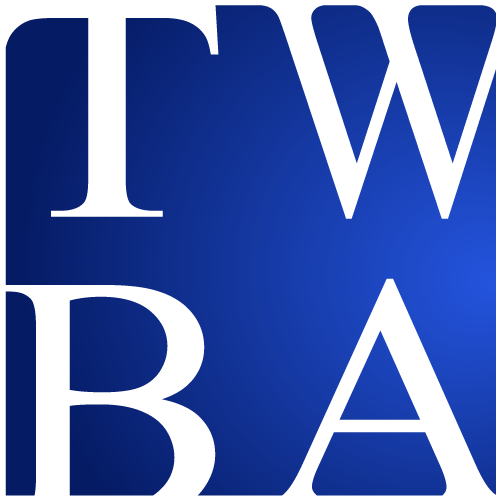


コメント