「こうあるべき」にサヨナラ!心の呪縛から解放され、自分らしく輝くための具体的ステップ
こんにちは。オンラインライフコーチングサービス「There Will Be Answers.」代表ライフコーチの常岡です。「ココロとアタマとカラダの声をぜんぶ聴く」をモットーに、あなたが本当に望む人生を歩むためのお手伝いをしています。
「~すべき」「~ねばならない」といった「こうあるべき」という思考に縛られ、生きづらさを感じていませんか?この記事では、そんながんじがらめの思考から抜け出し、もっと軽やかに、あなたらしく生きるための具体的な方法を、ライフコーチの視点から分かりやすく解説します。
この記事を読んで得られること
- 「こうあるべき」思考の正体と、それが生まれる心理的背景
- 「こうあるべき」思考がもたらす心身への影響
- 具体的な「こうあるべき」から抜け出すためのステップと実践的なワーク
- 思考の癖を見抜き、より柔軟な考え方を手に入れるヒント
- 自分らしさを見つけ、自己肯定感を高めるためのアプローチ
この記事が、あなたの「こうあるべき」という重荷を下ろし、新しい一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
1. あなたを縛る「こうあるべき」の正体とは? – なぜ私たちは囚われるのか
私たちは成長過程や日常生活の中で、無意識のうちに多くの「こうあるべき」という考え方(スキーマや固定観念とも呼ばれます)に影響を受けています。「母親ならこうあるべき」「社会人としてこうあるべき」「良い妻/夫はこうあるべき」など、その種類は様々です。これらは時に私たちを導く指針となる一方で、過度になると自己否定やストレスの原因となります。
「こうあるべき」思考が生まれる背景
「こうあるべき」という思考は、主に以下の要因から形成されると考えられています。
- 育った環境や教育: 親や教師からのしつけ、教えの中で「良い子とはこうあるべき」「こうするのが正しい」といった価値観が刷り込まれます。例えば、文部科学省の学習指導要領にも、規範意識を育むことの重要性が記されていますが、それが過度なプレッシャーとならないようバランスが求められます。
- 社会的な規範や文化: 所属する社会や文化が持つ共通の価値観や期待も、「こうあるべき」思考を形成します。「空気を読む」「協調性を重んじる」といった日本の文化も、その一例と言えるでしょう。
- 過去の経験: 成功体験や失敗体験を通して、「こうすれば上手くいく」「こうすると失敗する」という独自のルールを作り上げることがあります。これが固定化すると、新しい状況に対応しづらくなることがあります。
- メディアからの影響: テレビ、雑誌、インターネットなどから流れる情報も、理想像やあるべき姿のイメージを植え付けることがあります。
これらの「こうあるべき」は、ある程度は社会生活を円滑に送るために必要なものもあります。しかし、それが絶対的なルールとなり、自分や他人を厳しく縛り付けるようになると、心の負担が増大します。
【ライフコーチ的アドバイス】あなたの「こうあるべき」リストを作ってみよう

まずは、あなたがどんな「こうあるべき」に縛られているか、具体的に書き出してみましょう。「日常生活での思い込みに気づく」ことが第一歩です。
「~しなければならない」「~すべきだ」と感じることを、仕事、家庭、人間関係など、様々な場面で思いつくままにリストアップしてみてください。
例えば、「朝は早く起きるべき」「仕事でミスは許されないべき」「常に笑顔でいるべき」など、些細なことでも構いません。このワークを通じて、無意識だった自分の思考パターンが見えてくるはずです。
2. 「こうあるべき」がもたらす心と体への影響 – 見過ごせないデメリット
「こうあるべき」という思考に強く囚われると、私たちの心と体には様々なネガティブな影響が現れます。
- 慢性的なストレス: 常に「あるべき姿」と現実の自分とのギャップに悩み、プレッシャーを感じ続けることで、ストレスが蓄積します。厚生労働省の調査でも、職場や家庭でのストレスが心身の健康に影響を与えることが指摘されています。
- 自己肯定感の低下: 「こうあるべき」基準をクリアできない自分を責め、「自分はダメだ」と自己否定に陥りやすくなります。これが自己肯定感が低い原因の一つとなります。
- 行動の制限と機会損失: 「失敗すべきではない」という思い込みから新しい挑戦を避けたり、「こうすべきだ」という固定観念から他の可能性を見過ごしたりすることがあります。
- 人間関係の悪化: 自分だけでなく他人にも「こうあるべき」を押し付けてしまい、窮屈な関係性になったり、衝突が生まれたりすることがあります。
- 心身の不調: 過度なストレスは、頭痛、肩こり、不眠、消化不良といった身体的な症状や、不安、抑うつといった精神的な不調を引き起こす可能性があります。もし深刻な不調を感じる場合は、医療機関や専門家への相談を検討してください。
完璧主義によるストレスを感じている方は、この「こうあるべき」思考が強く影響している可能性があります。完璧を目指すこと自体は悪いことではありませんが、それが過度になると、自分を追い詰めてしまうのです。
【解説】「こうあるべき」思考の悪循環イメージ
「こうあるべき」という強い思い込みは、しばしば以下のような悪循環を生み出します。
- 「こうあるべき」という思考を持つ
- その結果、理想と現実の自分との間にギャップを感じ、苦しむ
- ギャップを埋められない自分に対して自己批判をしたり、ストレスが増加したりする
- (このストレスが心身の不調を引き起こすこともあります)
- 失敗を恐れたり、完璧でないことを避けたりするために、行動が制限されたり、新しい挑戦を回避したりする
- 行動できないことで達成感が得られず、さらに自己否定感が強まる
- そして、さらに「こうあるべき」という思考に囚われてしまう (①に戻る)
このように、一度「こうあるべき」という思考に捉われると、なかなか抜け出しにくいループにはまってしまうことがあります。
【ライフコーチ的アドバイス】その「べき」は誰のため?メリット・デメリットを天秤にかけてみる



あなたが抱える「こうあるべき」の一つを取り上げ、それが「本当に自分のためになっているか?」を問いかけてみましょう。その「べき」を守ることで得られるメリットと、感じるデメリット(ストレス、時間的制約、感情の抑圧など)を具体的に書き出してみるのです。
もしかしたら、その「べき」は他人からの期待に応えるためのもので、あなた自身を苦しめているだけかもしれません。他人軸から自分軸へ シフトするには、まずこの問いかけが重要です。
3. 【実践編】「こうあるべき」から抜け出すための具体的な4ステップ – 心の呪縛を解く方法
では、具体的にどのように「こうあるべき」思考から抜け出せば良いのでしょうか?ここでは、コーチングで用いられるアプローチを参考に、4つのステップで解説します。トレーニングのつもりで、ぜひ取り組んでみてください。
ステップ1:自分の「べき思考」に気づく – 感情と思考の観察
まず大切なのは、自分がどのような「べき思考」を持っているのかを客観的に認識することです。日々の生活の中で、「イライラする」「モヤモヤする」「罪悪感を感じる」といったネガティブな感情に気づいたら、その背景にどんな「こうあるべき」が隠れているかを探ってみましょう。
NVC(非暴力コミュニケーション)では、自分の感情とその元になっているニーズ(大切な価値観)に意識を向けることを重視します。例えば、「会議で発言できなかった自分にイライラする」という感情の裏には、「会議では積極的に貢献すべきだ」という「べき思考」と、「貢献したい」「認められたい」というニーズが隠れているかもしれません。
具体的なワーク:感情ジャーナリング
ネガティブな感情を抱いたときに、以下の点を書き出してみましょう。
- いつ、どんな状況で?
- どんな感情を感じたか?(怒り、悲しみ、不安、罪悪感など具体的に)
- その時、頭の中でどんな「~べき」「~ねばならない」という声が聞こえたか?
- その「べき」の裏にある、満たされなかった自分の本当の気持ちや願い(ニーズ)は何か?
これを続けることで、自分の思考パターンや感情の癖に気づきやすくなります。
ステップ2:その「べき」は本当に必要? – 根拠とメリット・デメリットを検証
気づいた「べき思考」に対して、それが本当に絶対的なものなのか、客観的に検証してみましょう。認知行動療法(CBT)では、非機能的な思考パターン(考え方の癖)を見つけ、より現実的でバランスの取れた思考に変えていくことを目指します。
具体的なワーク:思考の検証シート
| 問いかけ | あなたの答え(記入例) |
|---|---|
| その「べき」は、100%真実ですか? 例外はありますか? | 例:「常に完璧であるべき」→過去に完璧でなくても大丈夫だった経験は? |
| その「べき」を持つことのメリットは何ですか? | 例:安心感、達成感、他者からの評価など |
| その「べき」を持つことのデメリットは何ですか? | 例:ストレス、自己否定、行動の制限、人間関係の緊張など |
| その「べき」を手放したら、どんな変化がありそうですか? | 例:気持ちが楽になる、新しいことに挑戦できる、他人にも寛容になれるなど |
| もし親友が同じ「べき」で悩んでいたら、何とアドバイスしますか? | (客観的な視点で考えてみましょう) |
| その「べき」の代わりに、もっと柔軟で現実的な考え方はありますか? | 例:「完璧でなくても良い、ベストを尽くせばOK」「失敗から学ぶことも大切」など |
このワークは、固定観念を捨てるコツを掴むのに役立ちます。客観的に自分の思考を見つめ直すことで、絶対だと思っていた「べき」が、実はそうでもないかもしれないと気づけるでしょう。
ステップ3:新しい視点を取り入れる – 柔軟な思考を育む(NLP的リフレーミングなど)
「べき思考」に代わる、より柔軟で建設的な考え方(新しい視点)を見つけていきましょう。NLP(神経言語プログラミング)には「リフレーミング」というテクニックがあります。これは、ある出来事や状況に対する見方(フレーム)を変えることで、その意味合いや感情を変化させる手法です。
例えば、「仕事でミスをしてしまった。私はダメだ(べき思考:ミスは絶対にしてはいけない)」という状況を、「このミスから何を学べるだろう?次に活かせることは?(新しい視点)」と捉え直すのです。
具体的な方法:
- 視点を変える質問をする: 「もしこの状況をポジティブに捉えるとしたら?」「この経験から得られる教訓は?」「別の可能性は考えられないか?」
- 言葉を変える: 「~すべき」を「~できたらいいな」「~という選択肢もある」といったより柔らかな表現に置き換えてみる。
- ロールモデルを見つける: あなたが「こうありたい」と思う柔軟な思考を持つ人を見つけ、その人が同じ状況でどう考え、どう行動するかを想像してみる。
ステップ4:小さな「できた!」を積み重ねる – 行動を変え、自信につなげる
新しい考え方を取り入れたら、次は実際に行動に移してみましょう。最初から大きな変化を目指す必要はありません。「スモールステップで目標達成する」ことが重要です。
例えば、「人前で発言するのが苦手(べき思考:完璧に話せないなら黙っているべき)」という人が、「まずは会議で一言でも挨拶してみる」「短い質問をしてみる」といった小さな目標を設定し、それをクリアしていくのです。
小さな成功体験を積み重ねるメリット:
- 自己効力感(自分ならできるという感覚)が高まる: これが「自己肯定感 高める 具体的な方法」に繋がります。
- 新しい行動パターンが強化される: 脳は新しい経験を通して学習します。
- 「べき思考」の呪縛が弱まる: 「こうでなくても大丈夫だった」という体験が、古い思い込みを書き換えていきます。
これらのステップは一度で完璧にできるものではありません。繰り返し実践することで、徐々に思考の柔軟性が高まり、「こうあるべき」から自由になっていくのを感じられるでしょう。
【解説】「こうあるべき」から抜け出すステップの流れ
「こうあるべき」という思考から解放されるためのプロセスは、以下のような流れで進めることができます。
| ステップ | 内容 | 目指す状態 |
|---|---|---|
| Step 1 | 気づく (感情と思考の観察) | 解放された自分 (柔軟な思考・自己肯定感UP) |
| Step 2 | 検証する (根拠とメリット・デメリット) | |
| Step 3 | 新しい視点を取り入れる (リフレーミングなど) | |
| Step 4 | 行動する (小さな成功体験を重ねる) |
【ライフコーチ的アドバイス】「~してもいい」許可を自分に出そう



「こうあるべき」の反対は、「~してはいけない」という禁止であることが多いです。例えば、「弱音を吐くべきではない」という思い込みがあるなら、「たまには弱音を吐いてもいい」と自分に許可を出してみましょう。
「失敗すべきではない」なら「失敗してもいい、そこから学べばいい」と許可するのです。この「許可出し」は、自分に優しくなる練習です。小さなことからで良いので、自分に「~してもいいよ」と声をかけてあげてください。それが、「自分を大切にする方法 簡単」な第一歩です。
4. 「こうあるべき」を手放した先にある、あなたらしい生き方
「こうあるべき」という重い鎧を脱ぎ捨てたとき、あなたの目の前にはどんな世界が広がっているでしょうか?
- 心が軽くなり、ストレスが軽減される: 無用なプレッシャーから解放され、ありのままの自分を受け入れやすくなります。
- 自己肯定感が高まる: 「こうあるべき」という高いハードルではなく、自分の基準で自分を認められるようになります。自分らしさを見つける生き方が実現しやすくなります。
- 行動範囲が広がり、新しい可能性に出会える: 失敗を恐れず、本当にやりたいことに挑戦できるようになります。
- 人間関係がより豊かになる: 自分にも他人にも寛容になり、よりオープンで温かいコミュニケーションが取れるようになります。
- 人生の満足度が高まる: 他人の価値観や社会の期待に振り回されるのではなく、自分が本当に大切にしたいこと(価値観)に基づいて選択できるようになります。
これは、まさに他人軸から自分軸へのシフトというプロセスの先に待っている状態です。自分自身の内なる声に耳を澄ませ、それに従って生きることで、より充実した日々を送ることができるでしょう。
【ライフコーチ的アドバイス】あなたの「ありたい姿」を具体的に描いてみよう



「こうあるべき」を手放した先に、どんな自分になっていたいですか?どんな毎日を送りたいですか?「理想の自分になるには どうすればいいか」を具体的にイメージしてみましょう。ノートに書き出したり、イメージボードを作ったりするのも効果的です。
大切なのは、誰かの期待に応えるためではなく、あなた自身が心から望む姿を描くことです。この「ありたい姿」が、変化へのモチベーションとなり、進むべき方向を示してくれるでしょう。
まとめ:「こうあるべき」からの解放は、あなたらしい人生の始まり
「こうあるべき」という思考は、長年かけて形成されたものであり、すぐに完全に手放すのは難しいかもしれません。しかし、今回ご紹介したステップを意識し、日々の生活の中で少しずつ実践していくことで、必ず変化は訪れます。
大切なのは、完璧を目指さないこと、そして、自分自身の心の声に正直でいることです。生きづらさ解消のヒントは、あなた自身の内側にあります。
もし、一人で取り組むのが難しいと感じたり、より深く自分と向き合いたいと思われたりした際には、専門家のサポートを求めるのも一つの有効な手段です。ライフコーチは、あなたが「こうあるべき」という思い込みに気づき、それを手放し、本当に望む生き方を見つけるための伴走者となります。
この記事が、あなたが心の呪縛から解放され、自分らしく輝くための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
あなたの「こうあるべき」を手放し、本当に望む人生を歩み出しませんか?
「ココロとアタマとカラダの声をぜんぶ聴く」オンラインライフコーチングサービス There Will Be Answers. 代表ライフコーチの常岡です。
もしあなたが、
- 「こうあるべき」という思考に縛られて苦しい
- もっと自分らしく、軽やかに生きたい
- 頭ではわかっていても、なかなか行動に移せない
- 自分の本当の気持ちや望みがわからない
- 変わりたいけど、どうしたらいいかわからない
と感じているなら、一度お話ししてみませんか?
私のライフコーチングでは、NLP、CBT、NVCなどの心理学的なアプローチをベースに、あなた自身が持っている「答え」を見つけ出すお手伝いをします。
サービスの特徴:
- マンツーマンの丁寧なセッション: あなたのペースに合わせてじっくりとお話を伺います。
- 具体的な行動プランの作成: 気づきを行動に繋げ、変化を実感できるようサポートします。
- オンラインで全国どこからでも: ご自宅などリラックスできる環境でセッションを受けられます。
「こうあるべき」という思い込みを手放し、心から望む人生を創造していく旅を、一緒に始めませんか?
まずは、お気軽にホームページをご覧いただき、公式LINEからお問い合わせください。
あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。
ホームページ: https://terewillbeanswersx.com
公式LINE: https://lin.ee/wTcun6T
代表ライフコーチ 常岡
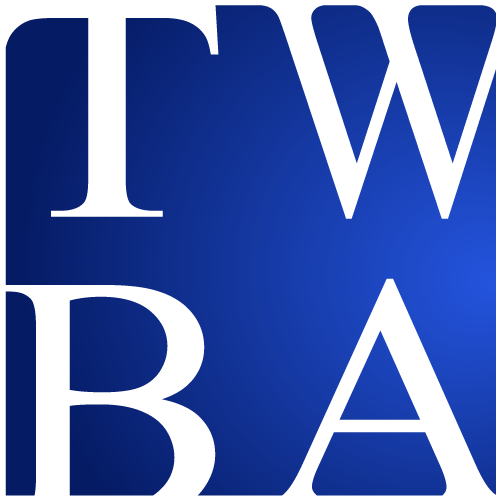


コメント