なぜ今、教育移住が注目されているのか?時代の背景と本質|「子供の未来」と「家族の幸せ」の選択肢
こんにちは!ライフコーチの常岡です。
「ココロとアタマとカラダの声をぜんぶ聴く」をモットーに、オンラインライフコーチングサービス『There Will Be Answers.』を主宰しています。普段は、人生の様々な場面で迷ったり悩んだりしている方々の、心の整理や次の一歩を踏み出すお手伝いをしています。私自身もマレーシアで一人の息子を育てている親として、子どもの教育や将来については、いつもアンテナをあちこちに伸ばしています。
さて、最近「教育移住」という言葉を耳にする機会が増えたと思いませんか?
インターネットやSNSを見ていると、国内外を問わず、「子どものためにもっと良い環境を」と考えて、思い切って引っ越しを決めたご家族の話が、以前よりずっと身近に感じられるようになりました。
どうして今、こんなにも「教育移住」が話題になっているのでしょうか?
ただのブームなのでしょうか? それとも、私たちの暮らしや考え方の変化が関係しているのでしょうか?
この記事では、ライフコーチとして、そして一人の親としての目線から、この「教育移住」という選択肢について、その背景にあるものや、私たちが本当に大切にしたいことは何なのかを、一緒に考えていきたいと思います。
もしあなたが、子供の教育環境の選び方で悩んでいたり、海外移住や子育てにかかる費用について知りたかったり、あるいは漠然と子供の将来に対する不安をどうにかしたいと感じているなら、きっと何かヒントが見つかるはずです。読み終わったときに、「なるほど、そういう考え方もあるのか」「うちの場合はどうだろう?」と、ご自身の家族にとっての幸せな選択について、すでに持っている答えに気づくきっかけになれば嬉しいです。
教育移住って何?どうして最近よく聞くの?
まず、「教育移住」って具体的にどういうことでしょう?
簡単に言うと、「子どもの教育環境を一番の理由にして、住む場所を変えること」です。日本国内の別の地域へ引っ越すことも、海外へ移り住むことも、どちらも含まれます。
選択肢も様々です。特定の学校、例えばインターナショナルスクールや、ユニークな教育方針を持つオルタナティブスクール、自然豊かな地方の学校などに入れたいという場合もあれば、もっと広く、自然体験がたくさんできる場所や、異文化に触れられる環境を求めて移住する、というケースもあります。
では、なぜ今、教育移住に関心が集まっているのでしょうか? いくつか理由が考えられます。
- 先の見えない時代への不安と期待:
世の中の変化は本当に速いですよね。グローバル化が進んだり、AIがどんどん進化したり。そんな時代に、「今まで通りの教育だけで、子どもたちは大丈夫かな?」と、少し不安を感じる親御さんは少なくないようです。
同時に、変化の時代だからこそ、子どもたちがすでに持っている素晴らしい可能性を信じ、それを最大限に引き出せる環境を、より積極的に探す動きが出ているのかもしれません。 - 「その子らしさ」を大切にする教育への関心:
みんなと同じが良い、という考え方だけでなく、「個性を伸ばす教育」を受けさせたい、と願う声が大きくなっています。また、これからの社会では語学力や多様な文化を理解する力、自分で考えて行動する力が大切になると考え、「グローバル人材を日本でどう育てるか」に関心を持つ方も増えています。今の教育システムに物足りなさを感じて、フリースクールやシュタイナー教育、モンテッソーリ教育など、日本にあるオルタナティブ教育の種類を調べて、子どもにぴったり合う場所を探す動きも活発です。 - 働き方が変わって、どこでも暮らせるように?:
特にコロナ禍以降、リモートワークがずいぶん広がりました。会社に行かなくても仕事ができるようになったことで、「別に都会に住まなくてもいいかも」と考える人が増え、地方や、場合によっては海外で暮らしながら働く、という選択肢が現実味を帯びてきました。地方への移住に関心を持つ人が増えているようです。これにより、家族が本当に望む暮らしを実現できる場所を選ぶ自由度が格段に上がったことも、教育移住を後押ししている面もありそうです。 - 情報が手に入りやすくなった:
インターネットのおかげで、海外の学校の情報や、地方暮らしの様子などが、昔に比べてずっと簡単に調べられるようになりました。SNSで実際に教育移住した人の体験談を読むこともできます。これにより、以前は考えもしなかった選択肢が身近になり、「もしかしたら、私たちにもできるかも?」と、可能性を受け入れる気持ちが自然と生まれているのかもしれません。
これらの理由がいろいろと組み合わさって、教育移住が「特別なこと」ではなく、一つのリアルな選択肢として考えられるようになってきているのでしょう。とはいえ、これらの情報に全く触れることの無い方もまだ多くおられることも事実です。必要な情報や流れが、必要な人に自然に集まってきているともいえるかもしれません。
【ライフコーチ的アドバイス①:あなたの「どうして?」を大切に】

教育移住、ちょっと気になるな…と思ったきっかけは何でしたか? 今の環境のどんなところに「ちょっと違うな」と感じていて、移住することで「どんな風になったらいいな」と思っていますか?
「なんだか良さそうだから」「周りもやっているし」という理由だけでなく、あなたの心の中にある本当の願いや、すでに決まっている方向性を、言葉にしてみませんか?
例えば、「子どもの自信を育てたい」「色々な考え方に触れさせたい」「家族でもっとゆっくり過ごしたい」など、具体的に書き出してみると良いかもしれません。この「どうして?」がハッキリすればするほど、教育移住が本当にあなたの家族にとって自然な流れなのか、腑に落ちる感覚で見極めやすくなります。
教育移住の「いいところ」と「大変なところ」
教育移住は、子どもにも親にも、人生の大きな変化をもたらします。だからこそ、決める前によく考えることが大切です。ここでは、教育移住の良い面と、少し大変かもしれない面を、私たち家族の体験も含めて、正直に見ていきましょう。変化には常に両方の側面がありますが、どちらも成長の機会として受け入れる視点が大切です。
良い面
- 日本では少ない教育のチャンス:
海外ならではのカリキュラム(例えば国際バカロレアなど)や、特定の教育方法、宗教に基づいた教育など、日本では選択肢が限られる教育を受ける機会が広がります。国内移住でも、その地域ならではのユニークな教育プログラムや、先生が一人ひとりに丁寧に関わってくれる少人数の学校が見つかるかもしれません。まさに求めていた環境に出会える可能性があります。私たちはマレーシアにくることで「多人種、多言語、多国籍」の中での教育が手に入りました。 - 言葉の力と広い視野:
特に海外に移住すれば、毎日外国語に触れることになるので、子どもの語学力アップには大きなプラスです。また、色々な国の文化を持つ人たちと交流することで、偏見なく物事を見たり、柔軟に考えたりする力が育まれることも期待できます。これは、将来どんな社会になっても役立つ、もともと持っている豊かさを広げる力ですよね。息子は今、日本のお友達とは日本語で、先生や日本人以外のお友達とは英語でコミュニケーションしています。語学のクラスでは中国語も学んでいます。 - 自分で考えて行動する力が育つ:
慣れない場所での生活や、違う文化に触れることは、子どもにとってはドキドキする挑戦の連続です。それを乗り越える中で、自分で考えて動く力、難しいことにも立ち向かう力、違いと対峙し、それをそのまま受け入れる心が自然と育っていくことがあります。私の息子もマレーシアで様々な文化背景をもつ先生方、お友達の中でケンカしたり遊んだりしながら課題を乗り越えていっています。 - 豊かな自然や地域とのふれあい(地方移住の場合):
都会ではなかなか味わえない、広い自然の中でのびのびと子育てができるのは、地方移住の大きな魅力です。地域の人たちとの温かいつながりの中で、子どもがたくさんの大人に見守られながら育つ、そんな安心感に満ちた経験もできるかもしれません。
大変かもしれない面
- お金がかかる: 特に海外移住の場合、学校の費用(インターナショナルスクールは国によっては高額なことも多いです)、定期的に日本と往復する飛行機代、ビザを取るためのお金、現地での生活費(物価が高い国もあります)など、かなりのお金が必要です。海外移住における子育ての費用は、どこに住むか、どんな生活をするかで全く違ってくるので、事前にしっかり調べて、計画を立てることが絶対に必要です。ただし、必要なものは必ず満たされるという信頼を持つことも、心の支えになるかもしれません。国内移住でも、引っ越し代や家を探す費用、新しく車が必要になることもあります。生活費は安くなっても、お給料が減る可能性もあります。「どのような生活を送りたいのか?」は教育移住を選択する際にも大変大きなポイントです。
- 新しい環境に慣れるまでが大変(子どもも親も):
言葉が通じない、文化や習慣が違う… 新しい環境に慣れるまでは、子どもも親もストレスを感じることがあります。子どもが学校に馴染むのに時間がかかったり、友達ができにくかったりすることも。親自身も、地域に溶け込むのに苦労したり、仕事がなかなか見つからなかったりする不安を感じるかもしれません。一方、こうした経験もすべてがプロセスの一部であり、最終的には家族の絆を深めるきっかけとできることも事実です。 - 今までの人間関係と離れてしまう:
仲の良かった友達や、頼りにしていた身内と、物理的に離れてしまいます。現地で新しい友達を作ることになりますが、言葉や文化の違いから、すぐに親しくなるのは難しいこともあります。「飲みに行こうよ!」「お茶しましょう!」とは簡単にいかないかもしれません。文化や背景の違う人間同士ならではの距離感と時間があります。焦らず、新しい出会いが待っていると信頼することも大切です。また、zoomやLINEなどのビデオ通話は大変心強いコミュニケーションツールです。私たちも実家の母と週に一度は顔を見て世間話をしています。母は私たちが日本にいた時よりも、多く孫の顔を見ているかもしれません。 - 情報集めや手続きが複雑: 特に海外移住の場合、学校選びから家探し、ビザの申請、銀行口座の開設、税金のこと、健康保険のことなど、やらなければいけない手続きがたくさんあって、情報もあふれていて大変です。公的な情報を確認することが大切ですが、言葉の問題もあって、信頼できる情報を探すのが難しいことも。国内、海外問わず移住先の自治体が提供している情報や、移住者向けのサポート制度などを上手に活用すると良いでしょう。すべての手続きはあなたに合ったペースで進むと信じて、焦らず一つ一つ丁寧に取り組むことが大切です。
- 公的機関・情報源(海外移住関連):
- 移住先の国の在日本大使館・総領事館
- 日本の外務省(渡航情報、手続き案内): https://www.mofa.go.jp/mofaj/
- 国税庁(海外転勤と税金など): https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm
- 日本年金機構(海外在住と年金、社会保障協定): https://www.nenkin.go.jp/service/scenebetsu/kaigai.html
- 公的機関・情報源(海外移住関連):
【ライフコーチ的アドバイス②:メリット・デメリットを「我が家の場合」で考えてみる】



今挙げた良い点と大変な点を、「ふーん、そうなんだ」と眺めるだけじゃもったいない! 大切なのは、「もし我が家が移住するとしたら、どうなるかな?」と、具体的に想像してみることです。そして、どんな状況になっても「私たちは大丈夫」という感覚を育むことです。
キラキラした面だけでなく、起こりうる大変なことも具体的にイメージして、「もしそうなった場合でも、必ず道はあると信じて、どう対処できるか?」まで考えてみましょう。心配を一旦横において、解決している未来を先にイメージしてみるといいでしょう。このプロセスを通じて、教育移住が自分たちの望む未来と一致する、現実的な選択肢なのか、より深く理解することができます。
教育移住で本当に大切なこと:それは「家族の幸せのカタチ」を見つける旅
教育移住を考えるとき、つい「どこの学校がいいかな?」「どんな教育を受けさせよう?」ということばかりに目が行きがちです。でも、ライフコーチの視点から見ると、それはもっと大きな旅の一部といえます。それは、「私たち家族は、本当はどんな生き方を望んでいるのか?」という、すでに心の中にある答えに気づき、それを現実として生きていく旅そのものなのです。
教育移住は「ゴール」じゃなくて「手段」のひとつ
教育移住に興味を持つきっかけは、「今の教育にちょっと不満がある」「子どもの将来がなんとなく心配」ということだったりしますよね。「子供の将来への不安を解消する方法」として、環境を変えることに期待する気持ち、よく分かります。でも、ここで一度立ち止まって考えてみたいんです。「引っ越したら、その心配は本当に全部なくなるのかな?」って。もしかしたら、その心配自体が、変化をブロックしているだけかもしれません。
例えば、「子どもの『自分でやりたい!』という気持ちを育てたい」という願いがあったとします。教育移住して、子どもの自主性を大切にする学校に入れるのは、良い方法の一つかもしれません。でも、もし家での関わり方や、親自身の考え方が変わらなければ、環境を変えただけでは、本当に望んでいる結果にならない可能性もあります。大切なのは、親自身がすでに安心し、満たされている状態でいることかもしれません。
コーチングでは、悩みの奥にある「ニーズ」を探究することを大切にします。「私たちが本当に求めていることは何だろう?」と、じっくり考えてみることが大切です。もしかしたら、その実現方法は「教育移住」ではなく、今の場所でできる工夫や、親の関わり方を変えることで、すでに手にしている幸せに気づき、望む状態に近づけるかもしれません。答えは外にあるのではなく、常に自分の中にあります。
「私たち家族、どうありたい?」をハッキリさせる
教育移住を考えることは、「私たち家族って、何を大切にしてるんだっけ?」と、自分たちの価値観に向き合うチャンスをくれます。それは、すでに心の中に描いている理想の状態を思い出す作業とも言えます。
- 子どもに、どんな大人になってほしい?(その理想像は、すでに子どもたちの内側に存在しているかもしれません)
- 勉強やスキルも大事だけど、それ以上に大切にしてほしいことは何かな?(例えば、優しさ、チャレンジする心、好奇心、色々な人を受け入れる気持ちなど。子どもの自己肯定感を高める子育てをしたい、というのも大切な価値観ですね。それは、親が自分自身を肯定することから始まります)
- 家族として、どんな時間を一緒に過ごしたい? どんな関係でいたい?(理想の家族関係は、今この瞬間から創り出せます)
- パパやママ自身の仕事や人生は、移住によってどう変わる? それは嬉しい変化?(変化を恐れず、望む現実を自分で選ぶと決めることができます)
これらの質問について、ご夫婦で、そしてもし可能なら子どもたちも一緒に、ゆっくり話し合ってみてください。何を大切にするかは、家族それぞれ、一人ひとり違って当たり前です。お互いの考えを否定せず、尊重し合いながら、「私たち家族にとってしっくりくる幸せの形」を共有していくプロセスそのものが、自然と最善の道(移住するしないに関わらず)へと導いてくれます。まるで、すべてのピースがカチッとハマるような感覚です。
気持ちを伝え合うことがカギ
この話し合いで一番大切なのは、家族みんながオープンに、正直な気持ちを伝え合うことです。特に、期待も不安も大きい移住という決断では、お互いの気持ちや「本当はこうしたい」という願いを、丁寧に伝え、理解し合うことが欠かせません。そして、感情的にならず、心と体が一致した静かな状態での対話を心掛けてみましょう。
ちょっと難しいかもしれませんが、「私はこう感じている(例:移住、ワクワクする! / ちょっと怖いな…)」「なぜなら、こうしたいから(例:子どもの可能性を広げたい! / 今の安定した生活を守りたい!)」というように、自分の気持ちとその理由を正直に伝えてみる。そして、相手の気持ちとその理由にも、じっくり耳を傾けてみる。そうすると、ぶつかり合うのではなく、「お互い、そう思っているんだね」とただ受け入れ合える、温かい話し合いができるようになります。
教育移住は、家族というチームで乗り越える大きな挑戦です。それは、「最高の教育」を探すことだけじゃなく、「最高の家族のあり方」をすでに実現している自分たちを発見する旅でもあるんですね。
【ライフコーチ的アドバイス③:家族で「未来の地図」を描いてみよう!】



ぜひ一度、家族みんなで、「理想の家族ってどんな感じ?」「5年後、10年後、どんな風になっていたい?」なんてことを話し合ってみませんか? 過去の出来事や未来への心配ではなく、「すでにそうなっている」理想の今をイメージするのです。
「どんなおうちに住んでいる?」
「休日はどんな風に過ごしている?」
「家族みんながニコニコ笑顔でいるのは、どんな時?」
「大切にしている言葉やポリシーは?」
大きな紙に、絵や言葉で「家族の未来地図」を一緒に描いてみるのも楽しいですよ。これは計画ではなく、すでに実現している世界を表現する作業です。この対話を通じて、家族がもともと持っている共通の価値観や、それぞれの願いが見えてくるはずです。この「未来地図」が、教育移住という選択肢を考えるときの、内なるコンパス、つまり自分自身の確かな感覚となるでしょう。
教育移住を考える前に:ライフコーチからの具体的なヒント
教育移住という大きな決断に向けて、焦らず、一歩ずつ準備を進めるための具体的なヒントをお伝えします。努力ではなく、自然な流れに乗る感覚で進めていきましょう。
Step1: 自分と家族のことを、よーく知る(思い出す)
- さっきの「未来地図」の話も参考に、家族で話し合って、何を大切にしたいか(教育のこと、暮らし方、人とのつながりなど)、自分たちの望みを明確にします。
- どうして教育移住を考え始めたのか、現状の何を変えたいのか、移住によってどんな素晴らしい状態を実現したいのかを具体的に書き出してみましょう。
- パパやママ自身のキャリアプラン、経済的な状況、健康状態なども含め、家族全体の現状を評価したり判断することを一旦おいて、ありのまま認め、客観的に把握します。不足はないという視点を持つことが大切です。
Step2: とにかく情報を集めて、比べる!(必要な情報はやってくると信頼する)
- 移住したい場所(国、地域、街)の情報をたくさん集めます。教育制度、学校の種類(公立、私立、インター、オルタナティブなど)、授業料、どんなことを教えているか、卒業後の進路などを比べてみましょう。心が惹かれる情報に注目してみてください。
- 暮らしの環境(安全か、物価はどうか、病院はあるか、気候はどうか、文化や言葉、地域の人たちの雰囲気など)も詳しく調べます。その中で暮らす自分たちを具体的にイメージしてみて下さい。
- インターネットの情報は便利ですが、誤りや古い情報も混ざっています。必ず、大使館や市町村役場、教育委員会、学校の公式サイトなど、信頼できる公的な情報を確認しましょう。個人のブログやSNSは、あくまで参考程度にして、そのまま信じ込まないように気をつけてくださいね。最終的には、自分の内なる感覚を信じることが重要です。
- ビザ・税金・社会保険のこと: 海外に移住する場合は特に、ビザの種類や取り方、現地の税金(所得税など)と日本の税金の関係、年金や健康保険がどうなるかなど、とても複雑です。弁護士さんや税理士さん、社会保険労務士さんといった専門家や、関係する役所に相談して、正確な情報を手に入れることが絶対に必要です。すべては最適なタイミングで整うと信頼しつつ、一つ一つ丁寧に取り組むことが大切です。国によってルールが全然違うので、必ず最新の情報を確認してください。
- 確認・相談できる場所の例:
- 移住したい国の日本の大使館・総領事館
- 日本の外務省: https://www.mofa.go.jp/mofaj/
- 国税庁(タックスアンサー、国際税務に関する情報): https://www.nta.go.jp/
- 日本年金機構(社会保障協定について): https://www.nenkin.go.jp/
- 確認・相談できる場所の例:
Step3: 選択肢を絞り込む(心がときめく選択をする)
- 集めた情報と、Step1で確認した家族の価値観や条件を照らし合わせ、候補となる場所や学校を具体的に絞っていきましょう。考えすぎず、直感を大切に。
- もう一度、良い点と大変な点を「我が家の場合」で考えてみて、心が「これだ!」と感じる、現実的な選択肢をいくつかリストアップします。
Step4: ちょっと行ってみる、体験してみる(その場の空気を感じる)
- もし可能なら、候補の場所に実際に行ってみて、街の雰囲気や学校の様子を自分の目で見てみるのが一番です。理屈ではなく、体で感じる感覚を大切にしてください。
- 夏休みなどを利用して、短い期間だけ子どもが現地の学校に通ってみる(サマースクールなど)とか、親子で短期留学してみる、あるいは数週間~数ヶ月くらい「お試し」で住んでみるのも良い方法です。
- 現地に住んでいる日本人や、移住した経験のある人に話を聞けると、もっとリアルな情報が手に入ります。その人たちの放つ雰囲気やエネルギーも感じてみましょう。
Step5: 決断! そして準備へ(すでに決まっていることを確認する)
- これまでの情報を全部踏まえ、家族で最終的にどうするかを決めます。これは新しい決定というより、すでに内側で決まっていたことを確認する作業に近いかもしれません。「移住する!」と決めた場合も、「今回はやめておこう」という結論になった場合も、どうしてそう決めたのか理由をハッキリさせて、家族みんなが心から納得し、これで大丈夫だという深い安心感を持てることが大切です。そこには疑いはもうない状態であることが大切です。
- 移住すると決めたら、具体的な準備(資金計画、ビザの申請、住居探し、学校への申し込み、引っ越し準備、色々な手続きなど)を始めます。すべては完璧なペースで進んでいると信頼しましょう。
- 心の準備も忘れずに。期待だけでなく、起こりうる困難やストレスについても家族で話し合い、どんな状況でも私たちは大丈夫だと確信できる、揺るぎない心の状態を保ちましょう。
【ライフコーチ的アドバイス④:小さな一歩から始めてみよう(自然な流れに乗る)】



教育移住って、本当に大きな決断ですよね。考えれば考えるほど不安になったり、「何から手をつければいいの…?」と途方に暮れたりすることもあると思います。そんな時は、「移住する? しない?」という大きな二択で悩むのを一旦やめて、「まず、心が軽くなること、ワクワクすること」から始めてみませんか?
「今度の週末、家族で理想の暮らしについて、楽しくおしゃべりする時間を作ろう」
「気になっている国の文化や景色を、リラックスして眺めてみよう」
「オンラインでやっている移住セミナーに、気楽な気持ちで参加してみようかな」
「子どもと一緒に、移住候補地の国の料理を、楽しんで作ってみようか」
どんなに小さなことでも、心が喜ぶことをまず動いてみることで、新しい情報や気づきが自然とやってきたり、モヤモヤしていた考えが腑に落ちる感覚になったりします。何かやってみて、そこから分かったことを元に、また次の小さな一歩を考える。この「小さな一歩」の繰り返しが、最終的に自然と納得のいく決断へと繋がっていきます。そして、パパやママが自分自身と調和し、満たされた状態でいる姿を見せること、それ自体が、子どもの自己肯定感を高める子育て、つまり子どもが本来の輝きを放つサポートになってきます。
まとめ:教育移住は選択肢の一つ。一番大切なのは「家族みんなの幸せ」を見つけること(すでに在る幸せに気づくこと)
ここまで、教育移住がなぜ注目されているのか、良い面や大変な面、そして考えるときに大切にしたい視点や具体的なステップについてお話ししてきました。
教育移住は、子どもにとっても家族にとっても、新しい可能性を開く素晴らしい選択肢の一つです。でも、それが唯一の正解というわけではありませんし、全ての家族にとって一番良い道だとは限りません。
一番大切なのは、流行や周りの声に惑わされず、「私たち家族にとっての幸せって何だろう?」という、すでに内側にある答えを中心に据え、家族全員で対話し、心が完全に一致する、納得のいく選択をしていくことです。外に答えを求めるのをやめ、内なる声に耳を傾けてみて下さい。
教育移住を考えるプロセスを通して、改めて家族が大切にしたいことを見つめ直し、お互いの気持ちを深く理解し合えたら、たとえ「移住しない」という結論になったとしても、その経験は家族にとって大きな(すでに持っている)財産となるはずです。不思議とすべては完璧な場所に収まるように感じます。
変化を恐れず、しかし焦らず流れに任せる。未来に向かって、あなたとご家族ならではの「幸せの形」をすでにそうなっているかのようにデザインしていく視点、つまり望む現実を今ここで生きる視点を持っていただけたら嬉しく思います。
あなたの「家族の未来」のデザイン、お手伝いします!
教育移住のこと、子育ての悩み、これからの働き方、夫婦の関係…生きていく中では、大きな選択に迷ったり、変化に戸惑ったりして、一人でグルグル考えてしまうことがありますよね。そんな時、あなたの心と頭の中を整理し、すでにあなたの中にある進むべき方向を見つけるお手伝いをさせていただけませんか?
私、常岡が運営するオンラインライフコーチングサービス 『There Will Be Answers.』 では、「ココロとアタマとカラダの声をぜんぶ聴く」 ことを何よりも大切にしながら、一対一で、あなたの隣で一緒に考え、伴走するパートナーとなります。
- 教育移住、考え始めたけど、何からどうすればいいか分からない…
- 家族で大切にしたいことがバラバラで、夫婦で意見が合わない…
- 移住したい気持ちと、今の生活を変えることへの不安で揺れている…
- 子どもの将来のこと、漠然とした心配をなんとかしたい…
- 自分の仕事や、これからの生き方も、もっとちゃんと見つめ直したい…
こんなお悩みはありませんか? コーチングの対話を通して、あなたの思考を深め、本質的な願いや本来の価値観を明確にし、自然な流れで具体的な次の一歩へと繋げていきます。難しい専門用語は使わず、分かりやすい言葉でお話ししますので、ご安心ください。答えはあなたの中にあります。
教育移住をするかしないか、その答え探しも含めて、あなたとご家族が心から「これがいい!」と思える未来をすでに実現しているかのように描き、自信を持って次の一歩を踏み出すために。まずはお気軽に、初回体験セッションをお試しください。オンラインなので、日本全国どこからでも、ご自宅でリラックスして、ありのままのあなたで受けていただけます。
あなたの「変わりたい」「もっと良くしたい」という前向きな気持ちに、心を込めて寄り添います。
▼詳しい情報や、お申し込みはこちらからどうぞ▼
オンラインライフコーチングサービス There Will Be Answers.
ホームページ: https://terewillbeanswersx.com
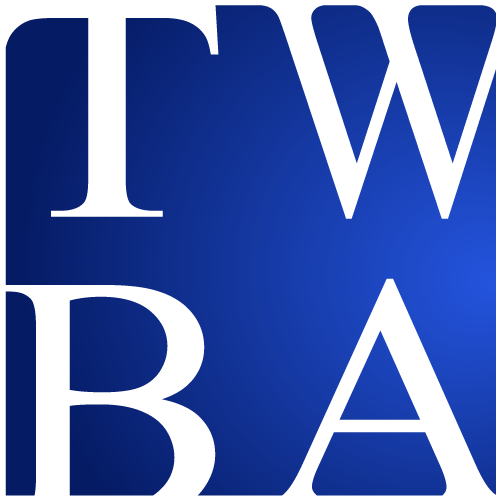


コメント